サーバーのトラブルにより、2020年11月以前のリンクが消滅してしまい、大変申し訳ありませんでした。
急遽2021年版でリニューアルして今日に至ります。(そろそろまた新装開店しようかナ...)
「行ってきた」「見てきた」から「お参りしてきた」へ
本サイトは京都の観光ガイドをするにあたって、イベントのご案内をしていたことから始まりました。
その後、御朱印がブームとなり、ガイドを担当させていただいているお客様の中にも御朱印をいただく方がどんどん増えていきました。
ガイドとしての現場での肌感覚からすると、御朱印ブームは中国・韓国などのアジア圏の女性が火付け役だったと思っています。
特に、中国、香港、台湾、シンガポールの女性が多いように思いました。
実際、どうして御朱印をいただくのか何人かのアジア圏の観光客に尋ねたことがあります。
彼女たちは、SNSで日本の御朱印についての情報が拡散していて、自分もそれを見て来ていると言っていました。
その後、日本の女性層を中心に御朱印をいただくことがひろく浸透していったように感じています。
もっとも、御朱印をブーム以前から老若男女問わず御朱印をいただく方々は一定数いらっしゃいました。

サイトの内容を京都の御朱印めぐりに特化したのは、以下の理由からで、それが今では本サイトの存続理由となっています。
御朱印はお参りした証になる
ただ、神社仏閣に行き、もちろんお参りもし、場合によってはお札やお守りなどもお買い求めいただく...
それでも一日を終えると、「あの神社に行ってきた」や「あのお寺を見てきた」となりがちです。
ところが御朱印をいただいてくると「どこそこにお参りしてきた」という気持ちになる方が大勢いらっしゃいます。

もちろん御朱印は買うものではありません。
私は300円にしろ500円にしろ、紙代やハンコ代ではなく、信仰心からの寄進・寄付行為だと考えています。(ご自身で意識されているかどうかは別として)
その気持ちに対しての、神社仏閣からの証として御朱印をいただくやり取りがあってこそ「お参りしてきた」という心境になる。
と、ガイドをしていて考えています。
つまり御朱印は、たんなる記念スタンプではなく、お参りした神社仏閣と心をつないだ証と言えるのではないでしょうか。
このサイトでは、そういう皆様の気持ちに寄り添う情報をお知らせするように心がけております。
お問合せ
お問合せについては以下のフォームにご記入ください。
なお[送信]ボタンをおすと、確認画面は出ずに、そのまま送信されます。






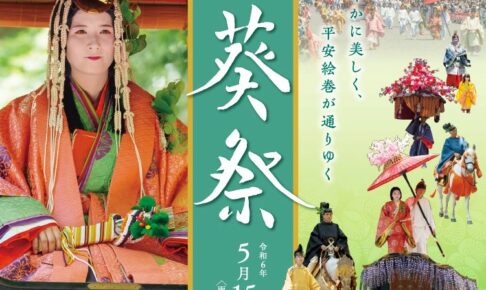






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a0e567.2e665276.17a0e568.39096fe0/?me_id=1350283&item_id=10000112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekkan-kyoto%2Fcabinet%2F2024-7cover.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)